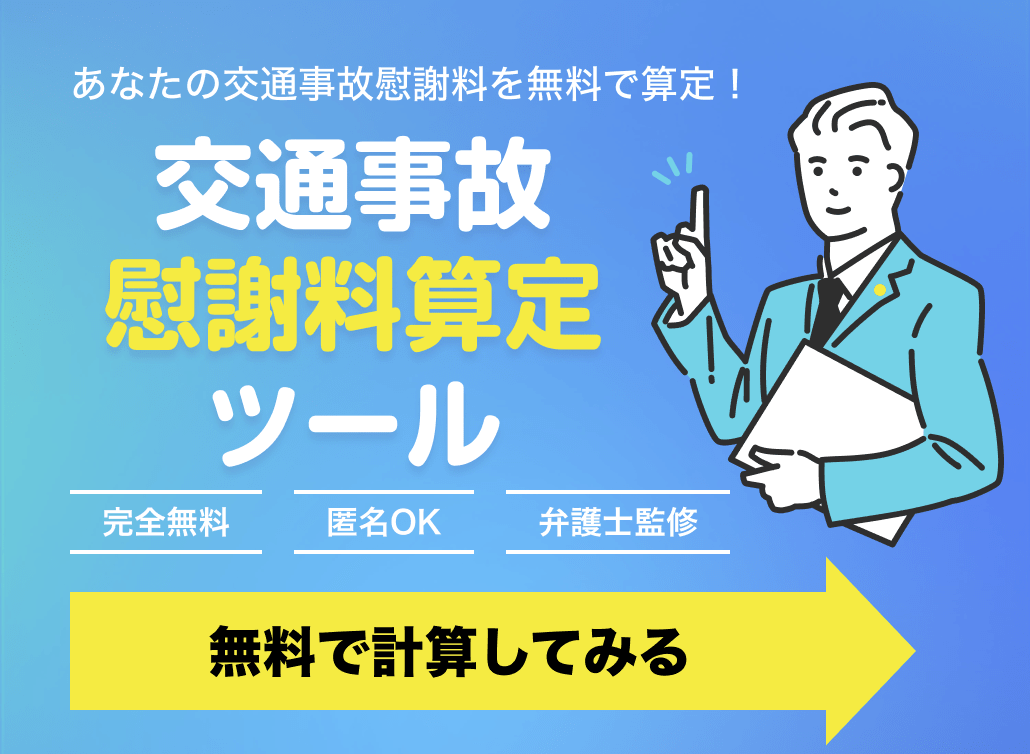長野県在住の交通事故被害者が知るべき慰謝料と保険会社の対応方法
- その他
- 交通事故
- 長野県

令和5年交通統計によると長野市内で発生した交通事故は965件で、死者数は5名、負傷者数は1107名でした。
長野県内では、毎年多数の交通事故が発生しています。もし長野県内で交通事故被害に遭ってしまったら、適切な慰謝料を取得するためにも弁護士に相談することをおすすめします。
本記事では、長野県内における交通事故の相談窓口や事故の発生傾向、損害賠償請求に関する注意点などをベリーベスト法律事務所 長野オフィスの弁護士が解説します。


1、長野県における交通事故対応の相談窓口は?
長野県内で交通事故の損害賠償請求などについて相談するなら、交通事故相談所または弁護士(法律事務所)を訪問しましょう。
-
(1)長野県内の交通事故相談所|何度でも無料で相談できる
長野県は、県内に3か所の「交通事故相談所」を設置しています。
各相談所では、以下のような事項について専門の相談員に相談できます。- 自賠責保険や任意保険の請求手続き
- 損害賠償の請求方法
- 過失割合の決め方
- 示談の進め方
- けがの治療
- 労災保険、健康保険、社会保険に関すること
交通事故相談所への相談は何度でも無料なので、誰でも気軽に訪問することができます。
ただし、交通事故相談所の担当者は、損害賠償請求を代理で行ってくれるわけではありません。請求の際は、ご自身で行うか弁護士に依頼することになります。 -
(2)長野県内の弁護士|損害賠償請求の対応を一任できる
交通事故の損害賠償請求に関する対応を一任したいなら、長野県で交通事故問題の解決実績がある弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、交通事故の損害賠償請求について一貫したサポートを受けられます。弁護士へ依頼する際には原則として費用がかかりますが、初回相談については無料で対応してもらえる事務所もあるため、ホームページなどで確認してみましょう。
2、長野県内における交通事故発生状況
長野県警察が公表している令和5年度の交通統計より、長野県内における交通事故状況を紹介します。
-
(1)令和5年は前年比増、ただし近年は減少傾向
長野県内における令和5年中の交通事故は5006件発生していて、前年比254件の増加となりました。
ただし、平成13年の1万4580件をピークとして、平成14年から令和4年まで21年連続で長野県内における交通事故発生件数は減少しています。
令和5年は21年ぶりの増加となりましたが、近年の全体的な傾向としては、交通事故は減り続けています。自動車両制御などの安全技術の向上や、交通安全の周知などが好影響を及ぼしていると考えられます。
なお、令和5年の長野県内における交通死亡事故による死者数は42人(前年比4人の減少)で、平成29年以降7年連続の減少となりました。 -
(2)追突事故と出会い頭の事故が多い
長野県内で令和5年中に発生した交通事故5006件のうち、車両相互の事故が4238件と8割以上を占めています。
その他は人(歩行者)対車両の事故が677件、車両単独の事故が89件、列車事故が2件です。
車両相互の事故の中でも、追突事故が1854件、出会い頭の事故が1332件と多数を占めています。前方不注意や、交差点や丁字路などでの急な飛び出しが交通事故につながっていることがうかがえます。 -
(3)損傷部位は頸部が最多
長野県内で令和5年中に発生した交通事故によって死亡した人は16名、負傷した人は4421名でした。
当事者が損傷した身体の部位としては、頸部が3227名(死者1名、負傷者3226名)と最多でした。なお、頸部の損傷によって死亡した人は、シートベルト非着用者であることが分かっています。
3、交通事故で重傷を負った被害者が請求できる主な損害賠償項目
交通事故で重傷を負った被害者は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益など、さまざまな項目の損害賠償を請求できます。弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償を請求しましょう。
-
(1)入通院慰謝料
入通院慰謝料は、交通事故によってけがをしたことに伴い、被害者が受けた精神的損害に対する賠償金です。
別表Ⅰ(骨折などの重症時)
入通院慰謝料の額は、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の別表Ⅰまたは別表Ⅱに入院期間と通院期間を当てはめて計算するのが一般的です。
骨折などの重症時には、別表Ⅰを用います。
入院期間
0月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 通院期間
0月0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338 10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335 11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332 12月 154 183 211 236 260 250 298 314 326 13月 158 187 213 238 262 282 300 316 14月 162 189 215 240 264 284 302 15月 164 191 217 242 266 286
別表Ⅱ(むちうち症・打撲・捻挫などの軽症時)
入院期間
0月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 通院期間
0月0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 023 203 5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214 10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209 11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204 12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200 13月 120 137 152 162 173 181 189 195 14月 121 138 153 163 174 182 190 15月 122 139 154 164 175 183
(例)
骨折をして1か月間入院し、その後4か月間通院した場合
→入通院慰謝料(裁判所基準)は130万円 -
(2)後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故によるけがが完治せず後遺症が残ったことに伴い、被害者が受けた精神的損害に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料を請求するには、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)の後遺障害認定を受ける必要があります。認定される後遺障害等級に応じて、後遺障害慰謝料の金額目安が下表のとおり決まっています。後遺障害等級 後遺障害慰謝料 1級 2800万円 2級 2370万円 3級 1990万円 4級 1670万円 5級 1400万円 6級 1180万円 7級 1000万円 8級 830万円 9級 690万円 10級 550万円 11級 420万円 12級 290万円 13級 180万円 14級 110万円 -
(3)逸失利益
逸失利益は、交通事故の後遺症によって労働能力が失われた場合に、将来にわたって得られなくなった収入を補填(ほてん)する賠償金です。
逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
※1年当たりの基礎収入:原則として、事故前の年収の実額です。ただし専業主婦(専業主夫)の場合は、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額を用います。
参考:「就労可能年数とライプニッツ係数表」(国土交通省) -
(4)その他
上記のほかにも、交通事故の被害者は、加害者側に対して以下のような損害賠償を請求できます。
- 治療費
- 通院交通費
- 入院雑費
- 付添費用
- 介護費用
- 休業損害
- 物的損害(車の修理費など)
お問い合わせください。
4、保険会社と示談交渉を行う際の注意点
保険会社との示談交渉を通じて適正な損害賠償を受けるためには、以下のポイントに留意しつつ対応しましょう。
-
(1)被害者に生じた損害を漏れなく集計する
すでに紹介したとおり、交通事故の被害者は、加害者側に対して多岐にわたる項目の損害賠償を請求できます。
被った損害の項目を漏れなく請求することが、適正額の損害賠償を受けるためのポイントです。自分だけでは気づきにくい損害もあるので、弁護士のアドバイスを受けましょう。 -
(2)適正な過失割合を主張する
保険会社は、被害者側にも過失があるとして、過失相殺による保険金の減額を主張してくることがあります。
交通事故の過失割合は、事故の客観的な状況に応じて決まります。保険会社が誤った事実認識により、不適切な過失割合を主張してくる場合は、客観的な事実に基づいて反論しなければなりません。
交通事故の過失割合は、損害賠償の額に大きく影響します。適正額の損害賠償を得るため、弁護士のサポートを受けながら適切な過失割合を主張しましょう。 -
(3)症状固定の提案を受けても、安易に応じない
保険会社は、被害者に対して「症状固定(=治療を続けても回復の見込みがない状態)しているのではないか」などと言って、治療費の打ち切りを提案してくることがあります。
被害者としては、保険会社から症状固定の提案を受けても、安易に応じてはなりません。症状固定に至ったかどうかを判断するのは医師であり、保険会社ではないからです。
もし保険会社から症状固定の提案を受けたら、その場で即答せず、弁護士や医師に相談しましょう。
5、交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害に遭ったら、速やかに弁護士へ相談しましょう。
弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。
- 賠償を請求できる損害を漏れなく集計できる
- 証拠の確保についてアドバイスを受けられる
- 後遺障害等級認定の申請を代行してもらえる
- 加害者側(保険会社)との示談交渉を一任できる
- 訴訟などの専門的な手続きにも対応してもらえる
- 弁護士基準(裁判所基準)に基づく請求により、損害賠償の増額が期待できる
交通事故の被害に遭ってしまったら、自分だけで抱え込むことなく、弁護士へご相談ください。
お問い合わせください。
6、まとめ
長野県内における交通事故は減少傾向にありますが、依然として年間5000件前後の交通事故が発生しています。もし長野県内で交通事故に遭ってしまい、相手に適切な損害賠償を請求したいとお考えの場合は、早めに弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、交通事故の損害賠償請求に関するご相談を随時受け付けております。初回相談と着手金は無料、相談しやすい体制を整えております。まずは、お気軽にベリーベスト法律事務所 長野オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています